1 3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進
自治体で廃棄物行政に携わっていた時、ごみ、主に一般廃棄物の減量を進める市民啓発を担当していました。そのころは、ごみの減量(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の3Rに、消費者目線で「リフューズ(レジ袋や過剰な包装など、不要なものは断る。)」を加えて「4Rの推進」を広めようと、あの手この手で広報をしていました。我ながら涙ぐましい努力をしたものです。
2 モノよりコト消費への移行がカギ?
行政は発信ベタとはよく言われることですが、日常生活に密着した「ごみ」の減量について、自治体が「生活環境・地球環境への影響」などの観点から訴えても、多くの方にはピンとこないものかもしれません。
3Rの中で、ごみ減量に最も重要なのは、流れの上流にある「リデュース」、つまりごみを減らすことと言われ、生ごみなどは水分をしぼるとかなり減量されるため各自治体で推奨しているところですが、忙しい現代人がいちいち生ごみを絞ることは、現実的に難しい面もあるかと思います。江戸時代には、鎖国をしていたためエネルギーをはじめ様々なものが輸入されず、ものを大切に使っていたとされ、生ごみも肥料や埋め立てて造成地にも転用するなど大いに活用されていたようですが、そうした時代とはかけ離れた話です。
廃棄物が増える大きな一因として、「大量消費・大量廃棄」の時代の流れがあります。近年、図らずも、服やバックや車などの商品・買い物よりも、心ときめく体験に時間とお金を使う「モノよりコト消費」の風潮が強まってきたせいか、あるいは格差社会の拡大で「新しくモノは買わない」方も増えたのか、人々が(特に高価な)モノに執着しない傾向が見られます。また、デジタル社会の進展により、バーチャルな世界で楽しめる方々が、リアルな物質である「モノ」への関心や執着を持たないということも想像できます。
余計にものを持たない、「リデュース」とともに、リユース品を扱うお店や個人間のリユース市場も活況です。モノへの執着が減るとともに、他人が使ったものを使いまわすことへの抵抗感が薄れているということなのでしょうか。
「ごみの減量」は、環境問題の根幹となることではありますが、いつの時代も、社会や人々の有り様と密接に結びついているものです。
↓
「行政書士樋口千恵事務所」ホームページへ


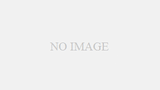
コメント